vol.29 Bashofu, Okinawa | 芭蕉布 沖縄
「今時こんな美しい布はめったにないのです。いつ見てもこの布ばかりは本物です。(中略)現存する日本の織物の中で、最も秀でているものの一つが芭蕉布なのです」
柳 宗悦『芭蕉布物語』より
It is rare to find such a beautiful piece of cloth nowadays. This cloth is always the real thing. Bashofu is one of the finest Japanese textiles in existence.
2020年4月からのコロナ自粛で海外はもとより国内への旅もできませんでしたが、そろそろ大丈夫かな?というタイミングで沖縄へ行ってきました。
Due to the Corona self-restraint from April 2020, I could not travel overseas or even domestically, but I thought it was time for me to go to Okinawa. I went to Okinawa just when I thought it might be safe to do so.

今回は本島中部に滞在し、まずは北部の「芭蕉布」の見学に。芭蕉はバナナの一種で、この繊維を使って織られた布が芭蕉布。芭蕉布会館があるのが、北部の大宜味村というところ。
海岸沿いを北上していくと、北部のやんばる国立公園のあたりから空気がガラっと変わり、あらためて沖縄は熱帯雨林の南国の島と感じます。芭蕉会館に着くと、芭蕉と南国の花とで異国のよう。
This time, we stayed in the central part of the main island and first went to visit the “Bashofu" in the northern part. Basho is a type of banana, and the cloth woven with this fiber is called Bashofu. The Bashofu Hall is located in Ogimi Village in the northern part of the island.
As you drive north along the coast, the air changes drastically around Yanbaru National Park in the northern part of the island, and you are reminded once again that Okinawa is a tropical island with tropical rain forests. When I arrived at Basho Kaikan, the basho (Japanese banana tree) and tropical flowers made me feel as if I was in a foreign country.


簡素な芭蕉会館は1階が見学コーナー、2階が工房となっており、まずは1階で機織りの道具や生地の展示と、芭蕉布の歴史のビデオを鑑賞。
The first floor displays weaving tools and fabrics, and a video on the history of bashofu is shown.

芭蕉布は、バショウ科の多年草イトバショウから採取した繊維を使って織られた布。日本の別名は「蕉紗」と呼ぶ。 沖縄県および奄美群島の特産品。薄くて軽く、張りのある感触から、汗をかきやすい高温多湿な南西諸島や日本本土の夏においても、肌にまとわりつきにくく、涼感を得られる。
ウィキペディアより
映像は、芭蕉の木から繊維を取り出し、煮詰め、紡いで糸にしていく作業。そして芭蕉布の着物を仕立てていく。
芭蕉布といえば、人間国宝の平良敏子さん。1921年生まれ、大正から昭和、平成、令和と100歳を越す今も現役で活躍されている。戦前は各地で作られていたが、その後は途絶える寸前であった芭蕉布の復興に尽力した方。この日も2階の工房で糸を紡いでおりました。残念ながら着物の展示はなく、写真で見るのみ。美しい民芸は、現代では高価すぎて庶民の手の届かない物になってしまったのか。
The video shows the process of taking the fiber from the basho tree, boiling it down, spinning it into yarn. Then, a basho cloth kimono is tailored.
Speaking of bashofu, the living national treasure Toshiko Taira, born in 1921, has been active in the industry since Taisho, Showa, Heisei, and 2025, and is still active at over 100 years of age. She has devoted herself to the revival of bashofu, which was made in many places before World War II but was on the verge of dying out afterwards. On this day, he was spinning threads in his workshop on the second floor.
Unfortunately, there were no kimonos on display, only pictures. Have beautiful folk crafts become too expensive and out of reach of the common people today?

大宜味村立芭蕉布会館
http://www.vill.ogimi.okinawa.jp/village_bashofu/
沖縄県指定無形文化財、経済産業大臣指定伝統的工芸品
後日談として、芭蕉布の着物は東京の大倉考古館での「-人間国宝・平良敏子と喜如嘉の手仕事-」にて見ることができました。
As a later note, the bashofu kimonos could be seen at “Handicrafts of Living National Treasures Toshiko Taira and Kinyoka" at the Okura Museum of Archaeology in Tokyo.

大倉考古館 

大倉考古館
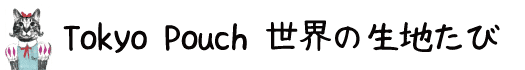
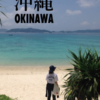
![THE [INDOOR] SESSIONS vol.2](https://tokyopouch.jp/wp-content/uploads/2022/07/展示会_SNSのコピー-100x100.png)
